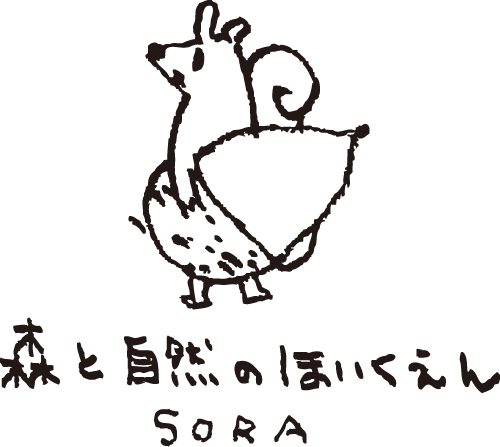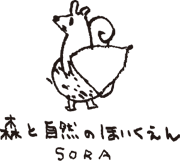森と自然の保育園SORAでは、2〜3ヶ月に1度、常勤/非常勤、職種にかかわらずスタッフ全員が参加する研修があります。
SORAの中では人生経験は一番長いですが、保育経験が短い私にとって、SORAでの研修は「心と体と頭に残る」学びを得ることが多い刺激的な機会です。
今回の研修では保育園のすぐ近くの公園でワークショップを行いました。 その公園は保育での散歩、探索でよく行く場所です。
今回の研修テーマ・狙いは
「子どもになって遊ぶ」
「子どもの近くにいる大人の役割とは」
「子どもになって遊ぶ」は、遊びを通して子どもがどんなことを感じているかを知る、想像するワークでした。
まずはアイスブレーク。公園を探索し、自分が気に入った葉っぱを見つけ、2人1組でお題での対戦。葉柄の長いほうが勝者などのお題が出題され、勝負し、盛り上がったあとは、五感を使って自然を感じることに。
視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚ごとにグループをつくり、それぞれの感覚に集中すると、自分はどんなことを感じるのか。その体験を通して子どもたちの気持ちや感覚を想像してみるワーク。
私は「触覚」グループに。
はじめは、手の感触を楽しもうと、グラウンドの砂を触ってみました。しかし、あまり気持ちよい感じがせず、水を混ぜたら手になじむかもと思いつきました。 水道のところに行く時、同じグループのスタッフが「足の感触もあるね」と一言。
「そうか。手だけではなく、足でも感じるのか!」とさっそく裸足になって水道のところへ移動しました。
アスファルトの歩道や細かな砂利のグラウンドには傷みを感じた分、クローバーの原っぱの上は、柔らかで、ヒンヤリとしてとても良い気持ち。
少しずつモノ(資源)と身体がダイレクトにつながる感触が楽しくなり、他にも裸足で触れたくなっていきました。

石垣を裸足で登るとしっかり岩を掴めます。桜の木も高いところまで登れて、鼻高々気分。子どもたちには普段「危険だから歩いてはいけないよ」と伝えている水道コーナーの高く狭い石垣も歩いてみたい衝動が抑えきれず、実際歩いてみると―――。
“落ちたら怖い”とヒヤヒヤする感じがまた刺激的。丈夫な靴は足を守るが、裸足は解放・自由・開拓の感覚を刺激してくるのでした。
裸足のまま、皐月の茂みへ。子どもたちの背の高さからは、森のように感じる大きな茂みです。茂みの中には、子どもたちが歩けるほどの細い小道ができています。いつもは子どもたちが出入りするのを見守っているだけですが、子どもになりきって入ってみました。
光が遮られて、薄暗く感じる茂みを、背を屈め、枝をかき分け、小枝を顔にぶつけながら進みます。そして、茂みを抜けると、同じグループのスタッフが、「(いないいない) ばぁ!」と、いつも子どもに向けるように笑顔で出迎えてくれました。
私はその笑顔をみてすごくほっとしました。そして、とても嬉しかった。これは予想外の感覚でした。茂みに入って抜ける3分もかからない時間の中で、自分が少しだけ緊張していたことに気が付きました。
子どもたちがチャレンジする時、きっと小さな体と心は緊張していることでしょう。そのそばに笑顔で見守っている大人がいたら、すごく安心できるのだと、私の心と体と頭にストレートに入ってきた瞬間でした。
公園に来ると、裸足になり、砂遊びをし、水を汲みにいく子どもたちの姿に、これまでは“脱いだ靴と靴下の位置を覚えて帰りに声かけしよう”と手順を確認していました。しかし、今回のワークでは、砂をつかむ、水を入れる、裸足で歩く、茂みを抜ける、それらの一つひとつの行動の中で、子どもたちの心が、身体とつながってしっかりと動いていること。そしてそのそばで笑顔で見守る大人がいることで、安心感と自信が生まれてくるのだと、本や知識からではなく、体験することから発見できました。
今回の研修を経て、私は「チャレンジを笑顔で見守る保育者でありたい」とはっきりと思いました。

この後も、子どもたちの年齢ごとになりきったワーク、子どもの感覚を保持しながら、「子どもにとってどんな大人であってほしいか」「どんな子に育ってほしいか」「そのために大人はどんなサポートが必要なのか」を話し合いました。一つひとつについて、延々と語りたいと思うほどの学びを得ました。
余談ですが、2年前の八ヶ岳のぐうたら村での研修の時に、土や生き物の多様性を知り、違う種類の生き物がそれぞれを支え合う姿を学びました。その時、多様性や共存とは、「多様性を認めねばならない」と言った倫理的な価値(だけ)ではなく、個々の生き物と全体が生き延びていくための必要条件、生存戦略なのだと実感しました。
ぐうたら村の研修の1年前に入職し、保育者としての未熟さに申し訳ない思いをしていた私ですが、「子どもも大人も色んな人がいることが大切。色んな人がいることで、それぞれも、全体も生き延びることができるのだ」と得心した機会となりました。
SORAでは、スタッフに対して、常にこのメッセージを出してくれています。この「どんな感覚や感情や意見でも大丈夫。そこから対話が生まれる」という姿勢が、研修による自由な学びや気づきを支えてくれていると今回の研修でも感じました。
Text : 綿引 幸代(ドーラ)